-遺産分割協議とは-
相続人間で行われる遺産の行き先を決める会議のことを言います。
この協議は、必ずしも直接会う必要はなく、電話で話し合った上で、「遺産分割協議書」を郵送でやりとりしてもかまいません。
相続した不動産の遺産分割方法とは
預貯金や現金であれば、相続人間での配分が決まれば比較的スムーズに分割ができますが土地や建物など不動産の場合、事情は異なり少々複雑になります。
不動産における遺産分割方法としては、以下4つの方法が一般的です。
| 現物分割 | 不動産をそのまま相続人の1人が取得する方法 |
|---|---|
| 代償分割 | 不動産を1人が取得するが、他の相続院に対し相応の金額を支払う方法 |
| 共有 | 不動産を相続人で共有する方法 |
| 換価分割 | 不動産を売却し、売却代金を相続人で分割する方法 |
実際には、相続する遺産は「老朽化した実家のみ」など、わずかな金額になるケースも少なくありません。
しかし長引く不況や増税を背景に、ささやかな額でも相続を期待している人も増えています。
そのため多額の資産がなくても、トラブルに発展している事例が多々あります。資産がないから、兄弟仲が良いからと安心してばかりもいられないのが実情です。
引き継ぐ実家に子が同居していたり、移り住む予定があるのであれば、「現物分割」や「代償分割」の方向で話し合いを進めるとよいでしょう。
誰も住む予定がなく、兄弟など相続人が複数いる場合、相続した不動産を売却して売却代金を相続人同士で分け合う「換価分割」であれば公平に分配できるのでトラブルを防ぐことができます。
換価分割を行う場合、実際に売却手続のできる相続人を選び、選ばれた相続人が自分の単独名義にした上で売却手続きを行うとスムーズです。
その際は遺産分割協議によって、誰が売却するのか、売却代金や期限、誰がどれだけ相続するのかを決めると良いでしょう。
◇遺産分割協議書の作成◇
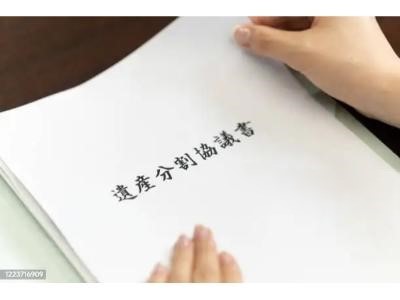
◇遺産分割協議における注意点◇

相続税の申告が不要の場合、相続登記の期限である3年以内には遺産分割協議を終わらせた方がよいでしょう。
相続した不動産を売却した場合に発生する所得税の優遇制度についても、相続から3年以内の縛りがあります。
とはいえ、話し合いがスムーズに進まないこともあります。
また、相続人の中に認知症の方がいる場合、意思能力が欠如しているとされ、遺産分割協議は無効となってしまいます。


