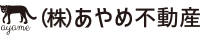-地上げとは土地を買い集めること-
地上げとは、特定のエリアの土地を買い集めて大規模な開発を行うための不動産取引手法です。
住宅地の分譲や再開発などの目的で、土地所有者と適切な交渉を行い、まとまった土地を取得する正当な取引手法を指します。
地上げ屋とは
「地上げ屋」や「地上げ業者」を公に掲げる不動産会社は珍しいものの、地上げは不動産取引における重要な業務の一つとなっています。
この業務では、所有権や抵当権、借地権、地役権、賃借権といった複雑な権利関係の調整が必要です。
これらの権利を適切に整理し、譲渡する側とされる側の双方にとって、トラブルのない取引を実現することが求められます。
宅地建物取引業法に基づき、不動産会社は取引当事者の代理や媒介を行う権限を持っています。
そのため、依頼を受けて地上げ業務を行うことは、宅地建物取引業者にとって通常の業務の一環です。
事業用不動産を売却する流れ
-簡易査定-
まず最初は簡易査定の依頼を出します。
データを元におこなう査定のため「机上査定」とも呼ばれており、住所や面積、間取り、公示地価などを参考にして査定金額を算出するものです。
ただし、あくまで簡易査定であるため、必ずしも査定時の価格で売却できるわけではありません。
次項の現地査定によって下がる可能性もあるので、参考程度に留めておきましょう。
-現地査定-
簡易査定の次に現地査定をおこないます。
弊社の担当者が実際に現地を訪問し、土地や建物の状態、接近条件や環境条件等をチェックした上で、査定金額を算出するものです。
査定結果は長くて1週間程度でわかるので、結果に問題がなければ売買契約に移ります。
-売買契約-
売買契約では、「売買契約書」と「重要事項証明書」を交わします。
担当者による重要事項説明を聞き、問題がなければ署名と捺印をし、契約は完了です。
-決済・引き渡し-
後日、弊社から代金のお支払いをおこないます。
なお、司法書士に所有権の移転登記を依頼する場合は、別途依頼料がかかります。費用は土地の規模にもよりますが、5万円前後が相場です。
移転登記が終われば、引き渡しが正式に完了となります。
-テナントへ連絡-
売却した不動産をテナントに貸し出し中の場合は、各テナントに所有者が移転した事実を伝えましょう。
テナントから敷金を預かっている場合は、弊社への引き継ぎ業務が必要です。
事業用不動産の買取ってもらう際の注意点
相場を把握する
事業用不動産を適正価格で売却するためには、売主が相場を把握できていることが大前提です。
価格の基準となる公示地価、過去の取引価格、固定資産税評価額などは、売主自身で確認可能ですので、できるだけ確認しておきましょう。
・公示地価および過去の取引価格
国土交通省が運営する「土地総合情報システム」で確認可能です。
・固定資産税評価額
各自治体から届く納税通知書に添付されている課税明細書で確認ができます。
課税明細書が見当たらない場合は、市区町村の役所で固定資産課税台帳の閲覧申請をしましょう。
あるいは、固定資産評価証明書を発行する手段もあります。申請書、本人確認が可能なものを役所に提出し、手数料を支払うことで発行可能です。
なお、事業不動産の価格は良くも悪くも相場価格とは乖離することがあります。
その理由は、事業不動産の価値をはかる上で「どれくらいの利回りが出るか?」が重要な指標となっているからです。
例えば、ロードサイドの事業用不動産の場合、
・視認性は良好か?
・交通量はどの程度か?
・駐車場を作るスペースはあるか?
・道路から敷地内への導線はスムーズか?
などが、現地査定の際にチェックされます。
所有期間に注意する
-土地の売り時を見極める上で「所有期間」が重要である理由は2つあります。-
1つ目の理由は、「長期間所有していると建物が老朽化してしまうため」です。
木造戸建住宅の場合、10年で価値が半分になり、20年でほぼ価値がゼロになります。土地に建物が建っているのなら、建物に値段がつくうちに売却しましょう。
2つ目の理由は、「所有期間によって譲渡所得税の税率が大幅に変わるため」です。
所有期間が5年を超えているか否かで、税率が倍近く変わります。
なお、親から不動産を相続した場合に、所有期間について知っておきたいルールが2つあります。
1つは、親の所有期間を引き継げることです。
例えば、親が6年間所有していた不動産を子が相続した場合、すでに所有期間は5年を超えているため、長期譲渡所得の税率が適用されます。
もう1つは、相続した土地を3年10ヶ月以内に売却すれば、相続税を取得費用に加算できることです。
これを「取得費加算の特例」と言います。取得費用が増えれば譲渡所得を圧縮できるので、譲渡所得税の節税につながります。
できる限り取得費用を多く計上する
取得費用とは、土地を売却する際の譲渡所得税を計算する際に用いられる用語で、土地や建物を取得するためにかかった費用を指します。
譲渡所得 = 取引価格 ー (取得費用 + 譲渡費用)
上記のように、譲渡所得は取引価格から取得費用を差し引いて計算するため、取得費用が多いほど譲渡所得税を減らすことが可能です。
つまり、最終的に手元に残る利益を増やせます。
取得費用を多く計上する上で知っておきたいのは、建物の取得費用が年々減っていくことです。
建物は年月の経過によって劣化するため、価値が減少します。そして、減少した分は減価償却費として毎年差し引くことになります。
例えば、木造の戸建住宅の価値は10年で半分ほどになると言われているため、3000万円で建てた木造戸建住宅が築10年の場合、建物の取得費用は概算で「1500万円」です。
また、土地の購入費や建物の建設費用以外に取得費用として計上されやすいものが以下となります。
・不動産業者への仲介手数料(取得時)
・売買契約時の印紙税(取得時)
・登録免許税(取得時)
・不動産取得税(取得時)
・登記時に司法書士へ支払った依頼料(取得時)
・取得時に支払った立退料(ない場合もある)
・取得時の建物の解体費用(ない場合もある)
・リフォーム費用(ない場合もある)
該当する取得費用をもれなく計上することで、譲渡所得を圧縮し、譲渡所得税を軽減できます。
できる限り譲渡費用を多く計上する
譲渡所得税を減らすことで、利益の手残りを増やすもう1つの方法が、譲渡費用を多く計上することです。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために要した経費を指します。
譲渡所得 = 取引価格 ー (取得費用 + 譲渡費用)
上記のように、譲渡所得を計算する際に用いられます。
つまり、取得費用と同様に、譲渡費用をできる限り多く計上することで、譲渡所得税の節税が可能です。
一般的には以下のものが譲渡費用として認められると言われています。
・不動産業者への仲介手数料
・売主が負担する印紙税
・地下埋設物の撤去費用
・建物の解体費用
・貸家を売るために借主に支払う立退料(ない場合もある)
特例や控除を利用して税負担を減らす
譲渡所得税を減らすことで利益の手残りを増やす方法は他にもあります。それが特例や控除を活用する方法です。
譲渡所得税の負担を軽減する特例や控除は複数あり、要件を満たして適用されれば、大幅な負担減となります。
例えば、以下のようなケースで特別控除の対象となる可能性があります。
| 特別控除の対象となり得るケース | 控除額 |
| マイホーム(居住用財産)を売却した | 3,000万円 |
| 公共事業などのために土地・建物を売却した | 5,000万円 |
| 特定住宅地造成事業などのために土地を売却した | 1,500万円 |
| 特定土地区画整理事業などのために土地を売却した | 2,000万円 |
譲渡所得の金額次第では所得額をゼロにすることも可能であり、その場合は譲渡所得税が発生しません。
土地開発事業・農地・不動産の有効活用・相続対策・空き家の売却・事業用用地・マンション用地など多岐に
わたり、賃貸や管理等は取扱わないため不動産売買に特化した不動産業者になります。
あらゆる不動産売買に対応いたしておりますのでお気軽にお問い合わせください。